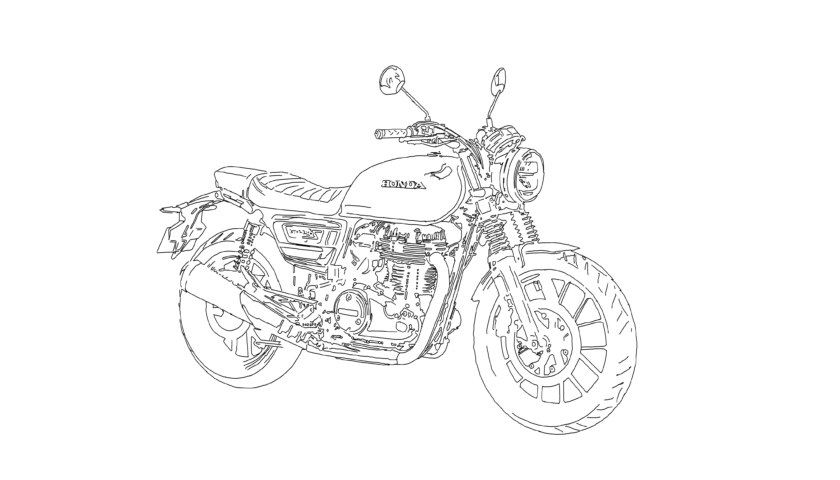逆操舵。バイク乗りにとっては難しいテーマではあります。
「そんなことしなくていい」「逆操舵では曲がらない」
こういった意見もあります。
ですが、みなさん、気づかずにやっているはずなので、こんなシーンを想像してみてください。
たとえば、走りながらちょっと右に移動したいとき。
方法としてはいくつかあります。
「タンクを抑えた膝に力を入れて、右に傾けることで曲がる」
「ハンドルごと右に傾けて曲がる」
「(左に)逆操舵を入れて曲がる」
「(顔の向きなどを使った)セルフステアで曲がる」
などです。
4つに共通しているのは、バイクの傾きがきっかけになっていることです。
バイクは傾くことで曲がります。
理由としてはタイヤの断面の大きさが違うことで、傾いた方向に曲がるという原理があり、キャンバースラストと呼ぶそうです。
また、タイヤの向きによっても曲がり、こちらはコーナリングフォースと言うそうです。
そして、4つの方法はいずれも右に傾けるためのアクションをしているわけですが、
「ハンドルごと右に傾けて曲がる」
この方法について考えてみてください。
「やったことがない」と思うかもしれないですが、ある程度のバイク人生と、自転車人生があるため、ほとんどの人が「ハンドルごと右に傾けてちょっと右に移動する」経験があるはずです。
そして、このときにハンドルをまっすぐというか、進行方向に対して垂直のまま、角度を入れずに右に動かすようなイメージで動かしているはずです。
これが逆操舵ということになります。
「逆操舵」というと、「(左に)逆操舵を入れて曲がる」という方法が注目されますが、こちらはサーキットの話でしょう。実際に真っ直ぐ走っていて、逆操舵を入れるのは「危ない」というイメージがあると思います。
一応、逆操舵を入れることによって、右に傾けることはできます。
ハンドルごと右に切る場合は、左にハンドルをはっきり切っているわけではありません。
操作側としてはまっすぐにしている気分です。
ですが、「右にハンドルを切ろう」とは思っていないはずです。
直感的に、右に切るのは危険だと感じているからです。なので、実際に試してみてほしいと思います。
ライダーの経験からくる直感で、そう思うはずだからです。
右に切らないように、腕を調整しています。多少左に傾くの許せるのです。
たとえば、運動の法則をなんとなく知っている我々は、まっすぐ走っている二輪の物体に対して、いきなりハンドルが切られると、ストップがかかるような感じがして危ないと思うはずです。
一方で、ハンドルを傾けない、もしくは少々反対側に傾けて、右に傾けるのは、そういった感覚は覚えないはずです。
また、ちょっと右に行きたいだけなのに、ハンドルを切るとずっと曲がってしまうような感覚もあるはずです。
実は、速度によってはちょっとの傾き(ライダーが気づかない程度)のあとにハンドルが切れていくのは、セルフステアで起こる挙動と一緒で、問題はありません。ただ、タイムラグがあるのです。
また、傾けない状態でもし右にハンドルを切ると、確実に左に移動します。
それと同じように、左にくいっと入れると、右に傾くので、右に曲がることができます。
サーキットのライダーが逆操舵を入れるのは、それがクイックに傾かせることができるからです。
セルフステアの場合はそれぞれの動きに時間がかかるので、待てないということです。
ですから、「公道ではセルフステア」が安全だと考えられます。
個人的には昔、「逆操舵で曲がる」という情報をどこからか手に入れて、高校生のころはモトクロスバイクを使い、逆操舵で曲がっていました。おそらくリーンアウトのようなポジションでやっていたと思うのですが、今思うと危険です。
ただ、「逆操舵でもバイクを傾ければ曲がる」という原理に関しては、体で覚えていたと言えます。
なので、「タイヤを傾ければ曲がる」も信じることができるし、「バイクを傾ければ曲がる」も信じることができました。ただ、最初に行う入力として、「曲がりたい方向にハンドルを切る」はあり得ません。
低速の場合は可能ですが、おすすめしません。
教習所のクランクが最初うまくいかなかったので、セルフステアにしたところ問題なくなりました。
そこで、教官に「クランクはセルフステアで曲がってますか?」と聞いたところ、「ハンドルを切っている」と言われ、ショックを受けました。
「ハンドルを切る」というのは、「どれくらい切るのか」という問題を抱えてますし、「どれくらい戻すのか」という問題もあります。また、先に切るのは逆に移動することになります。
おそらく、ここで説明した「ハンドルごと傾ける」をやっていたのではないかと、今になって想像してしまいますが、真相はわかりません。
私は通常、好みとして「セルフステア」が好きですが、そこにモトクロス的というか、クイックに少し移動したりする場合、逆操舵を利用した動きを積極的に使うのも悪くないと考えています。
それはハンドルを右に傾けるのもタンク入力でもステップ入力でも一緒です。
傾けるにはさまざまな方法があり、それをテクニックとして語られがちですが、バイクは何をやっても傾きます。
では、曲がるきっかけとなる入力についてまとめたいと思います。(右に移動する場合)
タンク入力
ニーグリップができる車種の場合、抑えたタンクを曲がる方向へぐっと力を入れれば、クイックに曲がることができます。
ステップ入力
タンク同様、ステップをきっかけとすることができます。個人的にはやったことはありません。
体全体の体重移動
たとえば一度脱力して(上側に腰を上げるようなイメージ)、もう一度置くときに傾ける側に微妙にずれることで傾けるとか、腰に力を入れて右に傾けるようにするなど。
ハンドル入力
本文で説明しているように、ハンドルごと右に傾ける方法です。私は教習所のスラロームで指導されました。
逆操舵
右に曲がりたい場合、左にハンドルを切る方法です。傾いていない状態で入れるのがコツです。
顔の向き
私がセルフステアでやっている方法です。多くの人が気づかずにやっている可能性があります。
たとえばまっすぐ走っているときに右を向くと、少ししてバイクは右に傾きます。その際、ハンドルは右には切れず、やや左に傾きます(気づかない程度)。
その後、ハンドルの力を抜いていると、右にハンドルが切れ始めます。
これは低速から中速まで、公道でのすべての速度域で使える方法です。
欠点は、顔の向きを変えるのは、予想して少し手前で行わなくてはならないことです。
ご存知のように、バイクは重心をバイクと同じにすることでまっすぐ走ります。
そして、スピードが落ちると傾きます。
最終的にどちらに傾くかは、わずかな重心の差です。
なので、曲がる方向を見続けることで、セルフステアが始まります。
面白いのは、カーブが近づくにつれて顔の向きは深くなり、出口に近づくにつれて浅くなります。
そのため、最終的にまっすぐを向いて、またまっすぐ走れるのです。
教習所の一本橋はこの原理を応用した練習です。
まっすぐ走るためには、顔の向きを動かしてはいけません。
でも、はじめての人は、傾いたりしたときに、顔の向きを変えてしまうのです。
なので、教官は「まっすぐ先を見て」と言いますが、これは「どんなときも前も見続けて」という意味なのです。
バイクに駆動力がある限り、前を見ていればバイクは傾きをやめます。
でも、どうしても最初はハンドルを切ったりしてしまう。
「なるべく時間をかけて」というルールは、低速になることでバイクはちょっとの重心の差で傾くからです。
わざと傾くような状態にさせて、それでもまっすぐ走るには、顔の向きが重要なのです。
というわけで、まっすぐ走るバイクが傾くと、旋回を始めることから、ライダーはあらゆる方法で重心を変えるための入力を行なっていることがわかっていただけたでしょうか。
Yamahaのロボットライダーのサイトには、「体重移動は必要ない」と書かれていますが、これは逆操舵を使っているためです。
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/urbanlegend
私は、いろんな入力を使って楽しめばいいと思います。
「これでなくてはいけない」ということはないし、「どうだ。俺はこの方法でやっている」と初心者に教える熟練ライダーやスクール講師のやり方には納得しないことが多いです。
それが正解なのだと思ってしまうのは、楽しみを奪うことになります。
大事なのはひとつ。「まっすぐ走っているときに、曲がりたい方向にハンドルを切る」だけはやめましょう。